
- アオダイショウ飼育に適したケージってどんなもの?
- どの大きさのケージを選べばいい?
- ケージ内はどんなレイアウトにしたらいい?

私、くま村長。
主に野外採集の日本産の爬虫・両生類の飼育者です。
当ブログは、私の実際の飼育経験に基づいて爬虫・両生類の飼育についてまとめています。
アオダイショウは特殊な生態で、ケージ選びにも注意が必要です。

確かに、ヘビの飼育ケージ選びって難しそう…

ということでこの記事では、アオダイショウの飼育ケージの『基本的な考え方』と『オススメ』、そして『ケージ内のレイアウト』についても言及していきます。
この記事では、以下の3点を深掘りして解説します。
- アオダイショウのケージの大きさの目安
- 要注意!脱走防止対策
- アオダイショウのサイズ別オススメケージ
→『誕生〜60㎝まで』『60㎝〜1m』『1m以上のアダルト個体』
この記事を読むことで、アオダイショウの飼育ケージに関する悩みが無くなります。

適切にアオダイショウを飼育できるようになるでしょう。

読み進めて確認してみてね。
アオダイショウのケージの前提【大きさと注意点】
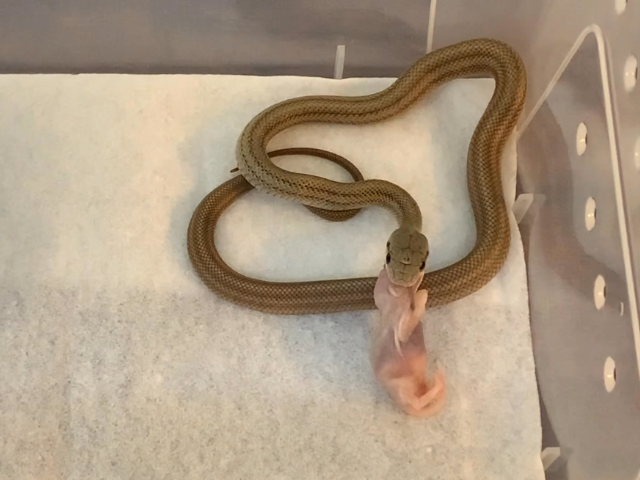
まずはアオダイショウのケージ選びの『基本的な考え方』を解説します。

前提となる考え方なので、確実に押さえましょう。
アオダイショウのケージ【大きさの目安】
☆ケージの大きさの目安☆
ケージの幅=『アオダイショウの全長の3分の1を下限』とする。

1mくらいのアオダイショウなら幅30㎝以上に、2mなら幅60㎝以上ってことですね。

アオダイショウは動き回らないので、カメやトカゲと比べて小さなスペースで飼育できます。
アオダイショウの最大サイズは2m、これでも60㎝水槽で終生飼育ができます。

余裕があるなら、90㎝サイズくらいで飼育して欲しいよ。
アオダイショウの最大体長はケージの大きさに比例する傾向があります。

つまり大きいケージで飼育すると、アオダイショウも大きく成長する可能性があるってことです。

以上を念頭にアオダイショウのケージを選べばいいんですね。
アオダイショウのケージ【要注意!脱走防止対策】
アオダイショウはとにかくすぐに脱走します。

ほんの少しの隙間で、出ていっちゃうの。

しかもパワーもあって、油断してるとこじ開けて出ていくんだぜ。

ということでアオダイショウのケージは、しっかりした蓋がありが押し開けれない強度の物を選んで下さい。
脱走したアオダイショウの未来は暗いです。
脱走対策をすることは、ストレスを与えない飼育方法につながります。

これを前提に、オススメのケージを次に紹介していきます。
【サイズ別】オススメ!アオダイショウのケージ〜レイアウト例〜

ということでオススメのケージです。

アオダイショウのサイズ別に解説していきます。
【アオダイショウにオススメのケージ】誕生〜60㎝までのサイズ
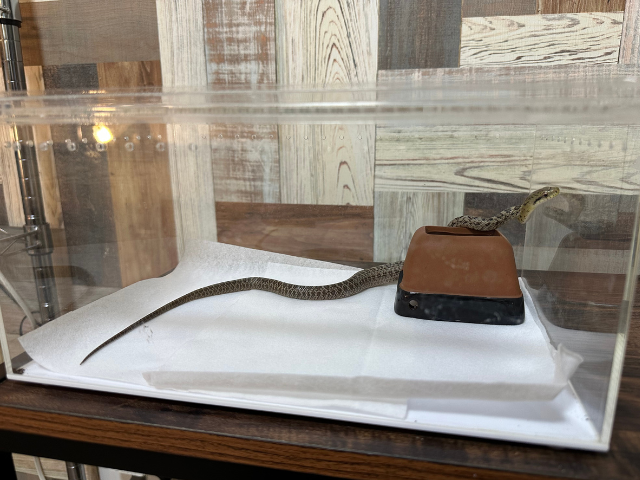
《幅30㎝・奥行20㎝・高さ15㎝》のレプタイルボックス。
床材はキッチンペーパーでウェットシェルターのみ設置。
幼蛇の内はレイアウトはシンプルに。
生まれたてのアオダイショウは体長30㎝くらいです。

この頃に大きいケースで飼育すると、アオダイショウにも負担があります。

あんまり広いと落ち着かないのよね。

何よりも大きいとメンテナンスのしにくいんですよね。

そこでオススメはレプタイルボックスです。
程度な大きさと、丸洗いもできるメンテのしやすさがあります。
>>レプタイルボックスはコチラから

レオパのケージとして有名ですが、蓋の機能が良く小型のヘビに向いています。
蓋が磁石で固定され、アオダイショウの力では開けることができません。
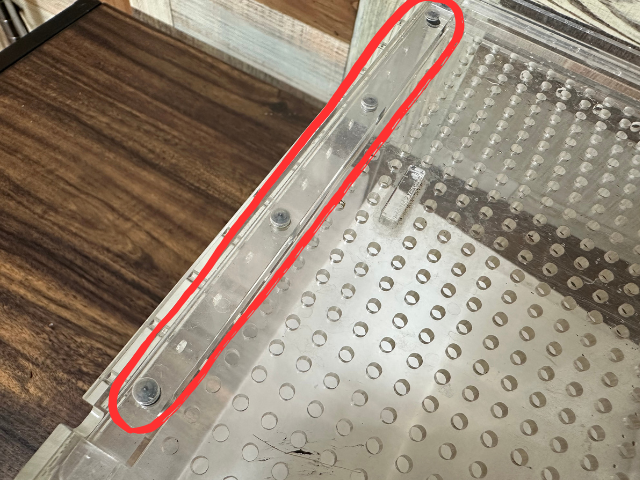

透明度が高くて観察しやすいのもいいですね。

アオダイショウが60㎝くらいになるまでは、このケージで飼育するといいでしょう。
【アオダイショウにオススメのケージ】60㎝〜1mまでのサイズ

《幅45㎝・奥行34㎝・高さ25㎝》のプラケース。
床材はヤシガラでウェットシェルターを設置。
上り木の代わりに突っ張り棒を設置。
アオダイショウは地上も這い回りますが、樹上性傾向の強いヘビでもあります。

自然では木に登ったり、壁にも垂直に登れるの。
立体活動ができた方が、運動ができていいのよ。

なのである程度高さがあった方がよく、体長が60㎝を超えたら大きめのプラケースを使うといいでしょう。
>>ここで使っているオススメのプラケースはコチラ

幅が45㎝あるので十分な大きさです。
高さもあるので、いろんなレイアウトが組めるのもいいんですよね。

ケージにあった蓋がついているのも安心ですね。
カチッとハマる頑丈な蓋だし。
プラケースの蓋は頑丈ですが、中蓋を締め忘れには注意が必要です。


とにかく安価で使いやすいプラケース。
アオダイショウ飼育では、どこかで必ず頼ることになるケージです。
【アオダイショウのオススメのケージ】1m以上のアダルトサイズ
アオダイショウが1mを超えると本格的に大人のサイズです。

そうなってくると、ケージも選択肢が広がってきます。
水槽【蓋の整備が肝心】

《幅60㎝・奥行30㎝・高さ36㎝》の水槽。
背面にコルクボードを貼り付けて、ボードに板を取り付けている。
床材はペットシーツ、水入れと上り木を設置。
60㎝までの水槽は、値段も安く十分なサイズがあり使いやすいです。

水槽自体が綺麗で、観賞性が高いのもいいですね。
>>ここで使っている60㎝水槽はコチラから
ポイントは蓋の整備です。

水槽はそれ単品で販売されていて、アオダイショウが脱走できない蓋はついていません。
そこで我が村では、以下のものを使っています。

この蓋はハープネット。
紹介している60㎝水槽にジャストフィットします。
>>ハープネットはコチラから
ただ置くだけでは、アオダイショウは簡単に押しのけます。

僕らのパワーを舐めちゃダメだよ。

どうしたらいいんですか?

以下の対策を取ってみて下さい。
▼ライトスタンドなどの重たいものをのせる▼


『おもし』を乗せるってことですね。

四隅が上がらないかチェックして下さい。
▼自転車の荷物バンドで固定する▼
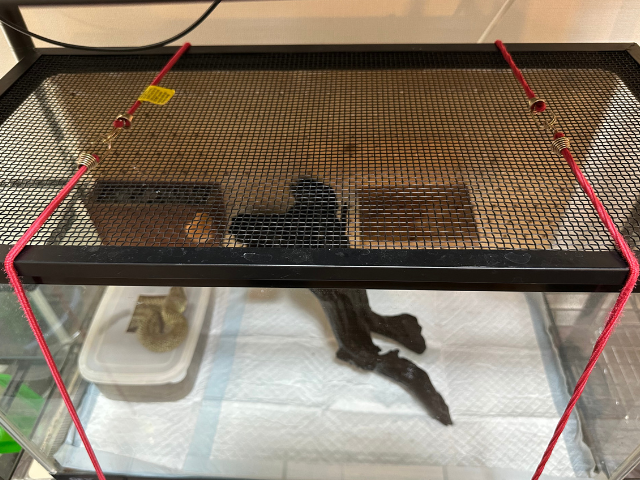

強力なのでアオダイショウでは押し除けることができません。
とにかく水槽を使うなら、蓋の問題を解決してから運用しましょう。
専用ケージ【高価だが完璧】

《幅31㎝・奥行30㎝・高さ44㎝》の寿工芸ヒュドラケース。
床材はペットシーツで水入れと上り木を設置。
高さを重視したケージ。

専用ケージのいいところは、前面が開くことです。
これによって餌やり、メンテナンスが非常にしやすくなります。

私たちは上から手を入れられるのは、ストレスが大きいのよね。

つまり専用ケースは、飼育者にとってもアオダイショウにとっても、いいケージってことですね。
>>ここで使っている専用ケージはコチラ

アオダイショウは樹上傾向が強いので、高さがあるケージならたくさん運動することができます。
まとめと関連
☆この記事で話したこと☆
- ケージの幅はアオダイショウの体長3分の1を下限とする。
- アオダイショウは脱走の名人、それに留意してケージを選ぶ
- 60㎝までの個体はレプタイルボックスが最適
- 1mまでの個体はプラケースで高さをつけて飼育する
- 1m以上は60㎝水槽、専用ケージを使う
▼この記事で紹介したオススメの飼育ケージ▼
>>幼蛇に最適なレプタイルボックスはコチラ
>>必ず使うことになるであろうプラケースはコチラから
>>水槽はコチラが使いやすいのでオススメ
>>60㎝水槽に合わせる蓋はコチラから
>>高さのある専用ケージはコチラから
▼くま村長のYouTubeコンテンツはコチラ▼








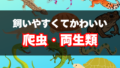
コメント